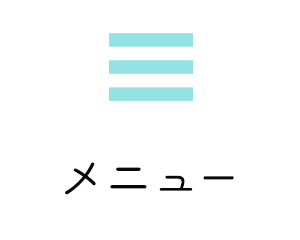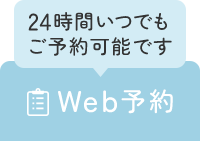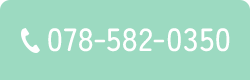- 動悸・息切れがする
- 動悸と息切れの違いと症状の特徴
- 動悸が続くときに考えられる病気と原因
- 息切れが続くときに考えられる病気と原因
- 動悸・息切れで病院に行くなら何科?
受診の目安 - 動悸・息切れの原因を調べる検査
- 動悸・息切れの治療と生活改善
動悸・息切れがする
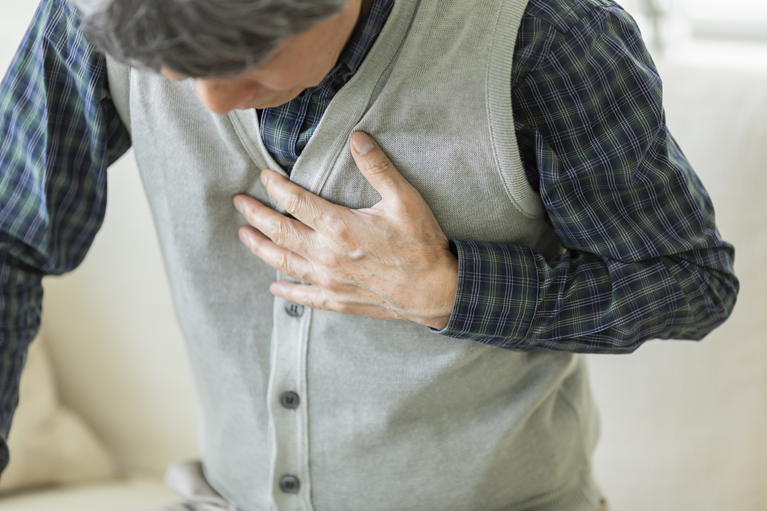 「動悸や息切れを感じる」「病院を受診した方がいいのか不安」といった悩みをお持ちではないでしょうか。
「動悸や息切れを感じる」「病院を受診した方がいいのか不安」といった悩みをお持ちではないでしょうか。
動悸や息切れは日常的なストレスや睡眠不足でも一時的に起こることがあり、休息を取ることで改善する場合も多くあります。しかし、重大な病気のサインである可能性もあるため、症状の特徴を理解し、適切な対応を取ることが大切です。動悸・息切れが心配な方は、神戸市北区の押谷クリニックへご相談ください。
動悸と息切れの違い・症状の特徴
動悸と息切れは、一見似ているようで異なる体の警告サインです。
動悸とは?
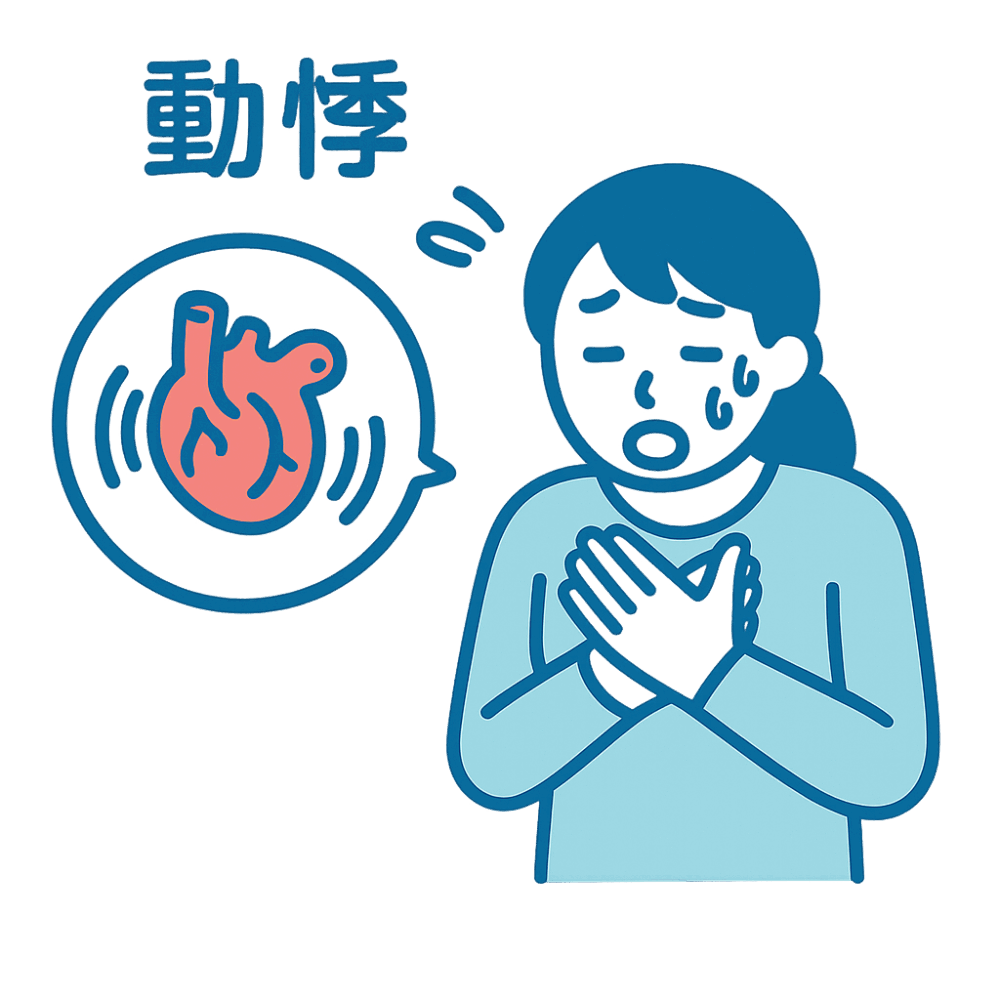 動悸は、心臓が「ドキドキ」「バクバク」と普段以上に激しく鼓動している感覚です。運動後やストレスを感じた時によく起こりますが、時には不整脈などの心臓の問題を示すこともあります。心拍が通常より速くなったり、一回一回の鼓動が強く感じられたりするのが特徴です。
動悸は、心臓が「ドキドキ」「バクバク」と普段以上に激しく鼓動している感覚です。運動後やストレスを感じた時によく起こりますが、時には不整脈などの心臓の問題を示すこともあります。心拍が通常より速くなったり、一回一回の鼓動が強く感じられたりするのが特徴です。
息切れとは?
 一方、息切れは、十分な呼吸ができず、酸素が足りないような感覚に襲われる症状です。階段を上った後などに「ハァハァ」となるのはよくある経験ですが、安静時に突然起こる息切れは要注意です。呼吸時に「ゼーゼー」という音が伴うこともあります。
一方、息切れは、十分な呼吸ができず、酸素が足りないような感覚に襲われる症状です。階段を上った後などに「ハァハァ」となるのはよくある経験ですが、安静時に突然起こる息切れは要注意です。呼吸時に「ゼーゼー」という音が伴うこともあります。
この2つの症状は密接に関連していることがありますが、動悸は主に心臓からのシグナル、息切れは呼吸器系からのシグナルと考えることができます。どちらも体からの重要なメッセージなので、特に原因が分からない場合や症状が続く場合は一度、医師にご相談ください。
動悸が続くときに考えられる
病気
 動悸の症状がある場合、以下のような病気が考えられます。
動悸の症状がある場合、以下のような病気が考えられます。
不整脈
不整脈の代表的なものとして、心房細動と発作性上室性頻拍があります。
心房細動は放置すると心不全や脳梗塞のリスクが高まるため、早期の治療が重要です。発作性上室性頻拍では、突然心拍数が150~200回/分まで上昇することがあり、注意が必要です。
これらの不整脈は、高血圧や糖尿病といった基礎疾患のほか、加齢、飲酒、睡眠不足、運動不足などが原因となります。
心不全
心臓の機能が低下して酸素を十分に運べなくなった状態です。これを補うために心拍数が上がり、動悸を感じます。食欲不振、倦怠感、足のむくみなどの症状も現れ、進行すると息苦しさを伴います。
循環器以外が原因の動悸
(甲状腺・貧血・低血糖)
甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで発症する病気です。特に女性に多く見られ、動悸の他にも手の震えや多汗、強い疲労感、体重減少などの症状が現れます。時には首の腫れによって気づくこともあります。
貧血
貧血では、体内で酸素を運ぶ量が減少するため、それを補うために心拍数が増加します。特に運動をした時に強い動悸を感じやすく、日常生活に支障をきたすことがあります。
低血糖
低血糖は、特に糖尿病の治療中の方に起こりやすい症状です。動悸と共に冷や汗やふらつきを伴うことが多く、危険な状態に陥る可能性があります。ブドウ糖を摂取することで予防できますが、根本的には処方薬の服用タイミングや食事管理を適切に行うことが重要です。
息切れが続くときに
考えられる病気・原因
 息切れの原因となる主な疾患には以下のようなものがあります。
息切れの原因となる主な疾患には以下のようなものがあります。
呼吸器系の病気による息切れ
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
主に喫煙が原因で、肺の機能が徐々に低下する進行性の病気です。受動喫煙もリスク要因となり、感染症で重症化しやすい特徴があります。
気管支喘息
アレルギーにより気管支に慢性的な炎症が起こる病気です。発作時にはヒューヒュー、ゼーゼーという音(喘鳴)を伴うことがあります。
循環器系の病気による息切れ
心不全
様々な心疾患が進行して起こります。高血圧、貧血、腎臓病、睡眠時無呼吸症候群なども原因となります。
狭心症
心臓の筋肉に血液を送る冠動脈の血流が不足して起こります。胸の締め付けと共に息切れを感じ、進行すると心筋梗塞のリスクが高まります。
不整脈
心臓の拍動のリズムが乱れる状態です。頻脈、徐脈、不規則な脈など様々なタイプがあり、原因や重症度に応じた治療が必要です。
その他の原因による息切れ
貧血
血液中の赤血球やヘモグロビンが減少し、体内の酸素が不足することで息切れが起こります。
腎機能障害
余分な水分を排出できなくなり、むくみや胸水がたまることで息切れの原因となります。
更年期障害
女性ホルモンの変化により自律神経のバランスが崩れ、ホットフラッシュ、息切れ、動悸などの症状が現れます。
甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンの過剰分泌により、頻脈や息切れなどが起こります。女性に多く、更年期障害と症状が似ているため注意が必要です。
動悸・息切れで病院に行くなら何科?受診の目安
 動悸や息切れを感じたら、症状の性質によって受診すべき診療科が変わってきます。
動悸や息切れを感じたら、症状の性質によって受診すべき診療科が変わってきます。
まずは内科を受診し、全身の状態を確認してもらうことをお勧めします。内科医が必要な検査を行い、症状の原因を特定し、さらに専門的な治療が必要かどうかの判断も行います。特に以下のような場合には、専門外来を受診することを検討しましょう。
心臓が原因かも?と思ったら
循環器内科へ
不規則な動悸、強い胸の痛み、急な息切れなどは、循環器科を受診してください。
心電図検査などの専門的な検査で、心臓の状態を詳しく調べることができます。
息苦しさが続くときは
呼吸器内科を受診
特に運動後や安静時に息切れを感じる場合は、呼吸器科の受診をお勧めします。肺機能検査などで、気管支や肺の状態を確認することができます。
動悸・息切れの原因を調べる
検査
 動悸や息切れの原因を特定するには、いくつかの検査を組み合わせて行う必要があります。当院で行える主な検査をご紹介します。
動悸や息切れの原因を特定するには、いくつかの検査を組み合わせて行う必要があります。当院で行える主な検査をご紹介します。
安静時12誘導心電図検査
手足と胸の12箇所に電極を貼り、心臓の電気的活動を記録します。約5分程度で終了する基本的な検査です。
ホルター心電図
携帯型の心電計を24時間装着し、日常生活における心臓の状態を継続的に記録します。一時的な異常や、通常の心電図では見つけにくい不整脈の発見に有効です。
胸部レントゲン検査
心不全の症状や肺の状態を確認する検査です。心臓の大きさや、肺のうっ血の有無なども分かります。
心臓超音波検査
(心エコー検査)
超音波を使って心臓の動きを観察します。心臓の収縮力、弁の動き、心筋の厚さなど、様々な情報が得られます。
動悸・息切れの治療と生活改善
治療方法は原因によって異なります。検査結果に基づいて、以下のような段階的な治療を行います。
軽度の場合:生活習慣の
見直しで改善
 症状が持続する場合は、脈拍をコントロールするための薬物療法を行います。また、原因となっている疾患に応じた治療も並行して実施します。生活習慣の改善だけでは管理が難しいと判断した場合に、この段階の治療に移行します。
症状が持続する場合は、脈拍をコントロールするための薬物療法を行います。また、原因となっている疾患に応じた治療も並行して実施します。生活習慣の改善だけでは管理が難しいと判断した場合に、この段階の治療に移行します。
重症の場合:専門的治療や
連携医療機関の紹介
 重症の場合や薬物療法でもコントロールが困難な場合は、ペースメーカーや植込み型除細動器の導入を検討することがあります。ただし、この段階になると専門的な治療が必要となるため、連携医療機関での治療をご案内することになります。
重症の場合や薬物療法でもコントロールが困難な場合は、ペースメーカーや植込み型除細動器の導入を検討することがあります。ただし、この段階になると専門的な治療が必要となるため、連携医療機関での治療をご案内することになります。
動悸・息切れは放置すると危険な場合があります。原因が単なる疲れやストレスの場合もありますが、重大な病気が隠れている可能性もあります。気になる症状がある場合は、お早めにご相談ください。